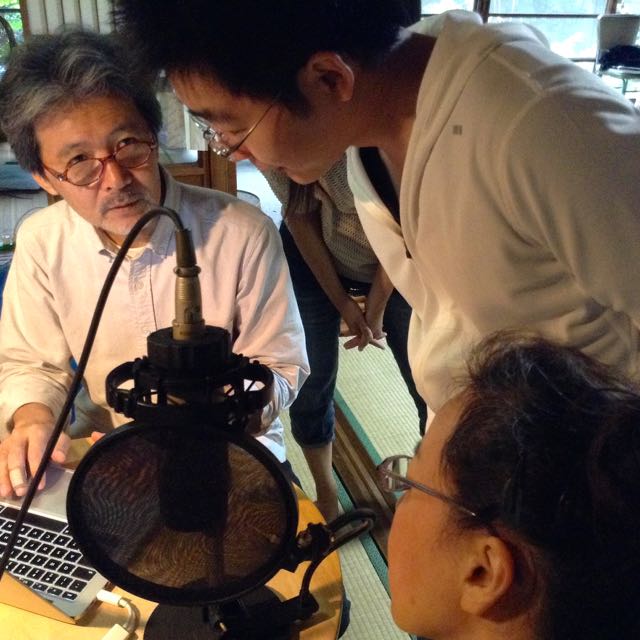肌にあたる海水の冷たさを思い唇がほころぶ
(C)2019 by MIZUKI Yuu All rights reserved
Authorized by the author
肌にあたる海水の冷たさを思い唇がほころぶ
水城ゆう
何度もなんども「これは夢ではない、リアルな現実に起こっていること」と確認している夢からさめると、自分がまだ生きていて、汗をかきながら浅い呼吸をしていることに気づいた。
呼吸をするたびに胸の奥のにぶい痛みが脈動するように感じるのは、錯覚だ。
最初は不整脈だと思った。だからハートクリニックに行ってみたりした。心電図をとり、ホルダー検査までした。「食道かもしれませんよ」という医師のことばを聞きながしていたことを、いまさら思いだす。
呼吸と連動する痛みは肋間神経痛だ。それがどのようなメカニズムで発生するのかは知らないが、何度も経験している。息を吸うのがつらいほどのこともあった。いま息を吸うときに痛みに身構えてしまうのは、たんなる痛覚記憶による反射反応にすぎない。
起きあがって枕元においたポーチから錠剤をつまみだす。ロキソニンひと粒で胸の奥の爆弾がいまのところ静まってくれるように思える。そのまま消えてなくなればいいのに、という常套的な願い言葉が頭の内側でこだまする。
備えておいた水筒の水で薬を飲みくだす。いまのところ、水は支障なく飲める。
ブラインドの角度を変えて光をいれると、椰子の木の影の角度からすでに午前七時をまわっていることがわかる。波打ち際をカモメが鳴き声も立てずにふわりと飛びすぎていく。風は強くないらしい。そのくせ波が高いのは、台風が近づいているという予報を裏付けしているのかもしれない。
今日はなにしよう。
問うまでもなく、うねりをともなった波が朝食前の私を呼んでいる。
その前に、コーヒーを一杯。
あと半年とか、あと数か月とか、限定的な余命を告げられたとき、人はそれまでとは違うなにごとかをやりたくなるらしい。行ったことのない場所に旅行するとか、食べたことのないものを食べに行くとか、会いたかった人に会いに行くとか、がまんしていた遊びに打ち興じるとか、なにか知らないけれど快楽にふけるとか。
私は違うことをやりたくなる前に毎日が違うように見えはじめたので、違うことをやる必要がなくなった。コーヒーをいれることだって、昨日と今日とでは感じが全然違う。コーヒーが変わるのではなく、自分が変わるのだ。昨日の自分と今日の自分は全然違う人間だし、違う現象だ。
そんなことは前から知っていたはずなのに、ちゃんとわかってはいなかった。限定的な余命を告げられなければそれが身体に落ちてこなかったなんて、どれほどおろかだったんだ、自分、と私は思う。
もっといえば、限定的な余命だって、すべての人がそうだし、私だって生まれて以来ずっとそうだったはずで、なにも医者から余命を告げられたいまにかぎったことではない。
ほんとにばか。
パジャマを脱ぎ、生理用ナプキンを引きだしから出そうとして、生理はすでに終わっていたことを思いだす。
ほんとにばか。かわいくすらある。
あと何日、波に乗れる? ウェットスーツのすきまにはいりこんでくる最初の海水の冷たさを予想しながら、私の唇はほころびている。