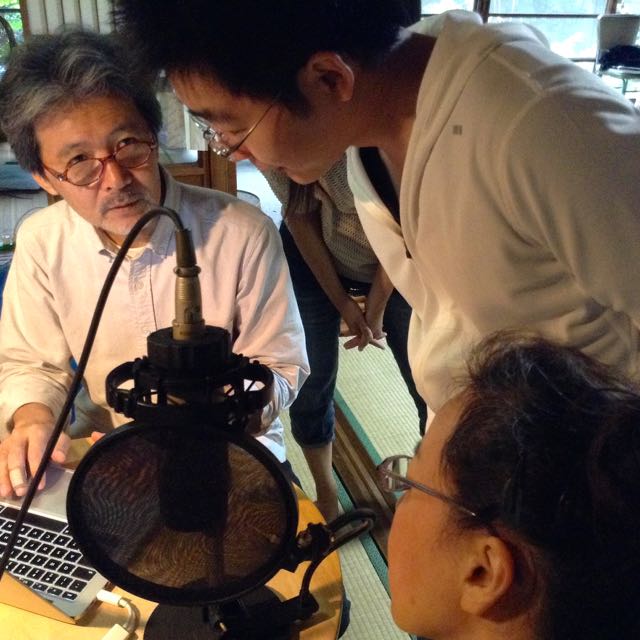沈黙の朗読――記憶が光速を超えるとき(3)
(C)2010 by MIZUKI Yuu All rights reserved
Authorized by the author
—– 朗読パフォーマンスのためのシナリオ —–
ちゃんと思いだした。子どものころから物忘れがひどかった。小学生のある日、ランドセルを忘れて手ぶらで学校に行った。母親が届けに来て、教室の入口で、同級生たちが見ている前で、こっぴどく頬をはたかれた。いまのいままでそんなことを思いだしたこともなかった。無意識の奥底にしまいこんでいた思いだしたくない記憶。たくさんの思いだしたくない記憶が、無意識の奥底にしまわれ、忘れさられている。物忘れをした恥ずかしい記憶がたくさん、記憶の奥底に忘れさられている。蛇口のパッキンを買わなければ。
私は歩きはじめる。おっさんどこへ行くんだよというだれかの声が聞こえる。腕を強く引きもどされる。
都会の学校に進学し、都会の会社に就職し、都会で結婚し、都会で家を持ったけれど、いつも思いだすのは野山のことだった。軒先に作られた燕の巣を見つめながら、畑の上の草はらで見つけた雲雀の雛のことを思っていた。街を歩きながら、風とともに山道を駈けおりたことを思い出していた。ひとり渓流をさかのぼり、岩陰にひそむヤマメを狙ったことを思い出していた。
列車が通過いたします。危険ですので、黄色い線の内側までさがってください。
列車が通過いた します。危険です ので、黄色い線 の内側
までさが
ってくだ
さい。
私はどこへ行こうとしているのか。
そうだ、蛇口のパッキンを買いに行くのだ。
だれかの怒号が聞こえる。
腕を強く引かれる。
私はそれをふりほどく。
蛇口のパッキンを買うのだ。
蛇口のパッキンを買うのだ。
危険ですので。
黄色い線の内側。
蛇口のパッキンは死。
蛇口のパッキンは死。
死とはなにか。
あのとき私が見ていたものの話をしよう。
ランドセルを忘れて親に怒られた私は、その夜、かけっぱなしの梯子を伝って、家の大屋根に登った。
屋根に寝っ転がって星を見ていると、自分がどこにいるのかわからなくなる。そんな経験はないかい? 自分が丸い地球に張り付いて、寝ているのか、地球にぶらさがっているのか、わからなくなってしまう。
ちっぽけな地球の表面に張り付いている私。宇宙のまんなかにぽっかりと浮かんでいる地球に張り付いている私。
地球、太陽系、銀河、銀河団、泡構造、超新星、膨張する宇宙、ブラックホール、ビッグバン、百数十億年のかなた。それが目の前に広がっている。永遠のかなた。
永遠ってなんだろう。宇宙のはてにはなにがある?
そんなことを考えていると、なにが原因で親にしかられたのかすっかり忘れてしまう。
でも、屋根から降りると、まだ怒っている父がいたし、父に気を使っている母もいたし、自分は怒られまいとこっちをうかがっている妹がいた。
そうやって地表の現実のなかで、今日まで生きてきた。
宇宙のなかのちっぽけな現実。喜んだり、悲しんだり、疲れたり、発奮したり、裏切られたり、愛したり、お金の心配をしたり。
この命も、いずれ消えていく。
死なない人はただのひとりもいない。偉大な人もちっぽけな人も、金持ちも貧乏人も、ひとしく皆、死を迎える。
沈黙に戻る。
村を離れ、都会に出たことを後悔してはいない。都会には都会の生活があった。ただ、夜中にこっそり裏口から抜け出し、ひと気のない公園をさまようとき、私の脳裏には谷川から沸き立つように舞い上がる羽化したばかりの蛍の光の渦が見えていた。降るような満天の星が見えていた。
いま、私は、都会の電車のホームで、だれかにつかまえられ、引きたてられようとしている手を振りほどき、妻にたのまれた水道の蛇口のパッキンを買いに行こうとしている。
ぼくの身体は軽くなり、ふわりと浮いて舞い上がる。
そのとき、ふいに私は
妻の
名を
思いだす。
青い空
と
白い 雲
(おわり)