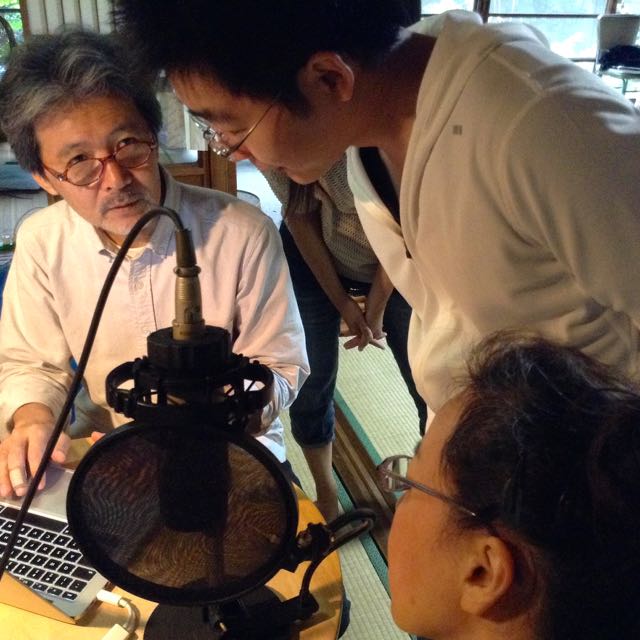現代朗読協会が新宿ピットインに登場した日
少し前のことになります。8月30日、火曜日。
以前から告知していたように、フリージャズピアノの第一人者である板倉克行さんのライブに、げろきょがゲスト出演してきました。
会場は日本のジャズシーンのメッカといっても過言ではない、新宿ピットイン。
私も何度か行ったことがあるはずなんですが、30日はまったく新鮮な気持ちで行ったせいか、まるで初めて来たライブハウスのように感じました。壁にはマイルス・デイビスやコルトレーンやエルビス・ジョーンズの写真パネルが、サイン入り(!)で貼られています。すごーい。
出演者は板倉さんのほかに、ベースふたり、タップダンサーひとり、サックスひとり、フルートひとり、ヴォイスひとり、という変則。
そこへ朗読がふたり、野々宮卯妙と照井数男。
私は当初、小型シンセを持っていこうと思っていたのだが、小型とはいえけっこう機材が重いので、簡易キーボードに持ちなおそうとして、さらに考え直した。こんなちゃちな機材で勝負できるわけがない。どうせちゃちなものを使うなら、身体で勝負できるものにしよう。
というわけで、ピアニカ一本ぶらさげていくことした。
7時半、開場。お客さんがパラパラと入ってくる。でもがら空き。そして半分くらいはげろきょ関係者。みんなありがと〜。
しかし、始まってみてわかったのだが、これだけのすんごいスリリングなセッションを、これだけの数の人しか目撃できなかったなんて、なんて贅沢というかもったいないというか。ま、しかし、商業システムや大衆はこれだけ鋭くとんがった先端表現を、もはや必要としていないんだろうな、という実感。
でも、私は必要としている。必要としている人が、少ないけれどいる。そしてここから次の時代が始まる。
セッションは板倉さんが出演者を次々と指名する形で、
「まるで学校みたいだな」
と、板倉さんも笑っていたが、まったくなにも決めごとのないフリーセッションが、次々と展開していく。
板倉さんが私にピアノをゆずってくれ、2曲、セッションに参加できた。そして、最後はピアニカで参戦。これが意外にも好評で、板倉さんも大変おもしろがってくれて、よかった。私も楽しかった。
そして野々宮はもちろん、照井数男もがんばってくれ、われわれげろきょが日本の第一線のフリーミュージシャンと張り合って一歩もひけを取らないパフォーマンスを展開できることが照明される現場を、私は目撃していた。
(水城・筆)